戦国時代は時代の青春だった
エンタメ・2020-11-27 18:11ヨーロッパでも中華でも、戦乱の時代は人口が減り、庶民は飢え、文化は低迷するもの。しかしなぜか日本の戦国時代、つまり室町時代から安土桃山時代前後の150年間は、人口は増え文化が昇華した時代なのであった。
人口については諸説あるが500万人から700万人ほど増加。文化であれば、茶道は戦国時代の千利休が完成させている。
ではなぜ戦国時代がこのような時代になったのかを考えてみよう。まず、農業技術が上がり二毛作などを行う農民が増え、豊かになっていった。それと服装、それまで庶民の服は麻であり戦国時代初期の頃、木綿は朝鮮などから輸入していた。当然値段も高かったはずだ。
それが戦国時代中期になると、兵衣として利用されるようになり、綿花の栽培が急速に増え、やがて庶民も着ることができるようになった。
木綿は防寒に優れているから、冬は綿入れの着物や、それまで藁の中で寝ていたのが、綿入れの布団に眠れるようになっていく。
戦国時代以前の時代は、貴族や僧侶が庶民の富集めて浪費するだけで、災害が起こっても、ほったらかしであったが、戦国時代は大名が領国のインフラを整えたり、隣の大名が農作物を盗みにきたら追い払うなどしないと、いざ合戦のときに農民は足軽として参加してくれない。よって農民や商人の面倒を見るようになる。すると豊かになり、文化が栄えるようになった。
また金銀の採掘技術が向上し、爆発的に採掘量が増えていった。特に銀は多く、戦国末期あたりになると、世界の3分の1の生産量と言われるほどであった。
この銀を使って、ヨーロッパやアジア諸国の交易が盛んになる。またタイ、フィリピン、ベトナム、カンボジアなどに日本人町を作り、武将や傭兵、商人が海外に進出していくグローバルな時代でもあった。
徳川幕府の270年間を保守的で老成していく時代だとすると、戦国時代の150年間は、荒々しい青春時代であったと言えるだろう。
プロフィール
おぐらおさむ
作家、漫画家。22歳で漫画家デビュー、35歳で作家デビュー、社会問題全般に関心が高く、歴史、時代劇、宗教、食文化などをテーマに執筆をしている。2004年、富山大学教養学部非常勤講師。 2008~2009年、JR東海新幹線女性運転士・車掌の護身術講師。空手五段。
-
 「おぐらが斬る!」ジャニーズから逃れるジャニーズたち 2023-09-16 20:20
「おぐらが斬る!」ジャニーズから逃れるジャニーズたち 2023-09-16 20:20 -
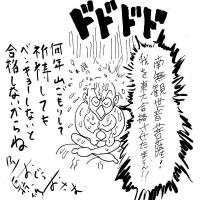 「おぐらが斬る!」人はなぜスピリチュアルや陰謀論を信じるのか? 2023-07-01 23:19
「おぐらが斬る!」人はなぜスピリチュアルや陰謀論を信じるのか? 2023-07-01 23:19 -
 「おぐらが斬る!」心中や自殺を肯定しがちなのは日本の文化であり伝統だが・・・ 2023-06-29 23:11
「おぐらが斬る!」心中や自殺を肯定しがちなのは日本の文化であり伝統だが・・・ 2023-06-29 23:11 -
 「おぐらが斬る!」見えないものは存在しない? それとも幻覚? 2023-06-25 20:08
「おぐらが斬る!」見えないものは存在しない? それとも幻覚? 2023-06-25 20:08 -
 「おぐらが斬る!」タイタニック見物で遭難した5人に、それほど同情できないわけ 2023-06-24 23:03
「おぐらが斬る!」タイタニック見物で遭難した5人に、それほど同情できないわけ 2023-06-24 23:03 -
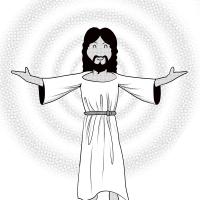 「おぐらが斬る!」世界の歴史を変えたイエス・キリストってちょっと困った人だった 2023-06-22 23:14
「おぐらが斬る!」世界の歴史を変えたイエス・キリストってちょっと困った人だった 2023-06-22 23:14 -
 「おぐらが斬る!」食のタブーななぜ生まれた? 神の命令より人間の都合? 2023-06-21 23:43
「おぐらが斬る!」食のタブーななぜ生まれた? 神の命令より人間の都合? 2023-06-21 23:43 -
 「おぐらが斬る!」広末涼子の不倫報道がにぎわっているが? 不倫バッシングをする人の心理とは? 2023-06-17 23:32
「おぐらが斬る!」広末涼子の不倫報道がにぎわっているが? 不倫バッシングをする人の心理とは? 2023-06-17 23:32 -
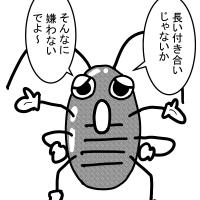 「おぐらが斬る!」日本人はなぜゴキブリを怖がるのか? 2023-06-16 23:05
「おぐらが斬る!」日本人はなぜゴキブリを怖がるのか? 2023-06-16 23:05 -
 「おぐらが斬る!」どうも宇宙人って知的じゃないらしい(苦笑) 2023-06-14 23:25
「おぐらが斬る!」どうも宇宙人って知的じゃないらしい(苦笑) 2023-06-14 23:25
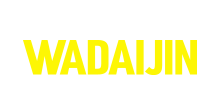


 閉じる
閉じる